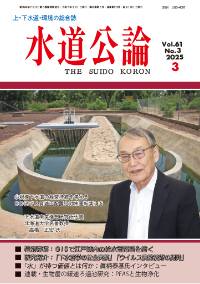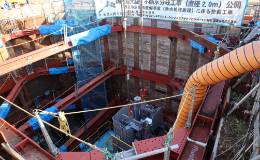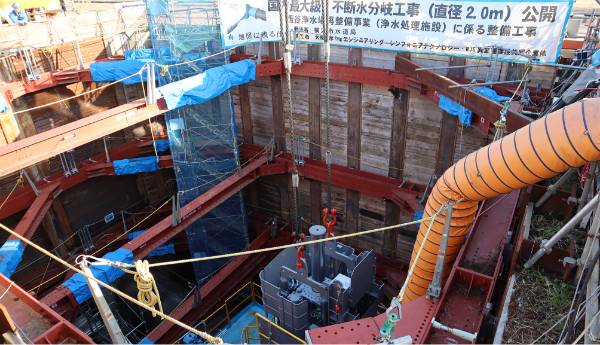表紙の人 下水道未来構想研究所代表 北海道大学名誉教授
高橋 正宏 氏
2100カ所を超える日本の下水処理場のうち、処理日量3000立方㍍以下の小規模処理場はその半数を占めている。これらについて、地方部の急激な人口減少のため、更新費用や運転経費を下水使用料で賄えていないケースも多く、必須の生活インフラである下水道そのものの存続が危ぶまれている。そこで一貫して下水道の研究者として歩んでこられた下水道未来構想研究所代表の高橋北海道大学名誉教授に、運転経費の削減といった具体的事例や今後の小規模下水道のあるべき方向性などを聞いた。
高橋 正宏(たかはし・まさひろ)氏 プロフィール